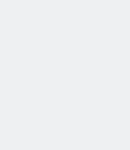『ハーパーコリンズ・ジャパン、101円~400円(アダルトラノベ)』の電子書籍一覧
1 ~20件目/全20件
-
「100ドル? 本気で言ってるの?」私はお酒にむせそうになりながら言った。
バーで飲んでいた私に、見ず知らずの男が声をかけてきたのだ。
うちに来てくれたら――そしてセックスしたら――100ドルあげるよ、と。
憤慨して答えに窮していると、後ろから低く柔らかい声がした。「1000ドルではどうかな」
そう言ったのは、ダンディでセクシーで、見るからに裕福そうな男性だった。
もう、ふたりともやめて、と言うかわりに私は冗談を返した。「2時間で5万ドルよ」
するとダンディは革の小切手帳を取り出すと、さらさらと数字を書き込んだのだ。
えっ? どうしよう……。いったい彼はわたしに何をしようというの……?
“お金で買われた女”として、彼の意のままに身体を嬲られる――
そんなシチュエーションに自分がどれだけ興奮するか、私はまだ気づいてもいなかった。 -
ブルースはわたしを離してくれない。40代半ばで、申し分ないルックスの敏腕CEOは、秘密の性癖を完璧に操るわたしを手放したくないのだ。太く硬いペニスをコックリングに締めつけられたまま、恥ずかしい体勢をとらされ、わたしがイクまで奉仕させられ、あげくのはてに放置される。それが彼の望むことだから。けれど、クレメント・ジョンズという優秀でハンサムな社員の出現によって、ある変化が生じていた。クレメントは会議中でも臆面なくわたしをランチやデートに誘う。気づいていながらもポーカーフェイスを保っていたブルースは、ついに我慢の限界に達したのか、わたしを社長室に呼びつけると、壁に押しつけて後ろから突き上げ、激しく射精した。自ら性奴隷を望むくせに、雄がテリトリーを主張するみたいにマーキングする彼を、わたしは嫌いになれない。でも、クレメントのセクシーな身体や声にも、抗いがたい魅力を感じる。彼とファックしたい、と思う。ブルースの執着、以前関係を持ったクライアントのアレックスの再訪、そしてまだ何も知らないクレメント――わたしは自己嫌悪に陥りながらも、狭いオフィスで男たちのザーメンにまみれ、溺れていく。
-
富と美貌に恵まれた令嬢レティシアには、社交界デビュー以来、求婚が殺到。
だが、最大の関心事である花婿候補たちとの肉体的相性を知る術がなく、途方に暮れていた。
やがて思いついたのは、彼らを秘密のピクニックに誘うこと。
これなら付き添いの目のないところで思う存分、相性を試せるわ。
招待状を出した数日後、求婚者の一人、ラングストン子爵が屋敷を訪ねてきた。
広い肩、引きしまった腰、鍛えあげられた腿とふくらはぎ。服を着ていてもにじみ出る、男らしい力強さ。
まるで肉欲を形にしたような男性だ。
レティシアが震える膝を深く折って優雅に会釈すると、子爵は誘惑的な視線を投げた。
「いったいきみは、ピクニックで何をするつもりだ?」
顔を赤らめつつ計画を告白したレティシアに、子爵は言った。
「きみと花婿候補たちとの逢い引きの見張り役を引き受けよう。ただし……」 -
リリー・サンドリッジは、夫亡き後、数々の愛人と浮き名を流す美貌の公爵未亡人。
ある日、彼女のもとを1人の青年が訪れる。名前はアーサー・チャットマン。
彼はうやうやしく名刺を差し出すと、仰天の申し出をした。
「僕にセックスを教えてほしいんです」
何をばかなことをとリリーが一笑に付すと、彼は真剣な面持ちで言った。
「僕はいずれ妻を娶らなければいけない。けれど僕のモノは大きすぎて、きっと新妻を驚かせてしまう――処女を怖がらせることなく愛し合う方法を、僕に伝授してほしいのです」
リリーは言葉を失った。はじめは、それほどまでの彼の持ち物について。
そして無垢な青年の、未来の妻への優しさに。気がつくとリリーは頷いていた。
うら若き乙女が、初夜の恍惚のなか、もう夫なしでは生きていけないと思うほどの技量を彼に授けよう。その代わり、私は若くみずみずしくそそり立つモノから溢れる樹液を、
一滴残らず搾りとり、味わいたい。口でも、身体の奥深くでも……。 -
私の恋人はライアン。男っぽくてワイルドなタイプで、
女友達のケイの恋人はショーン。いかにも科学者っぽい、線の細さがセクシーなタイプ。
あるとき4人でキャンプに行き、私たちは同じテントに寝ていた。
耳のすぐ横で聞こえるショーンの寝息に、私はどうしようもなく感じていた。
ライアンが反対側から手を伸ばしてきて、疼きの源を探り始める。
「や、やめてよ……」囁き声で抵抗するのに、彼はますます大胆になって、
ふとんの下で私の脚を割り、硬いモノを突き入れてきた。
2人ともわかっている――ショーンもケイも目を覚ましていることを。
私をイカせながら、ライアンはショーンに見せつけているのだ。
ほら、おまえも彼女とやりたくないか、と。
そしてケイにも。おれなら、きみをこんなふうにイカせてやるよ……と。 -
貴族の養女ミラは美しい娘に成長したが、黒い妖精に“欲望”という呪いをかけられてしまう。
ミラを完全に満たしてくれる者に出会うまで、常に身体の疼きに苛まれるというのだ。
そんなある日ジェラードとアランという2人の美貌の戦士がミラの屋敷の前で出会う。
かつて2人は友情以上の関係で結ばれた仲だったが、黒い妖精によって、
“誰かを完全に満たすまでは決して結ばれない”という呪いをかけられていた。
3人は、互いこそが呪いを解く鍵だと確信したが、3人でどう“満たし合う”というのか……。
答えはなくとも、ミラを日夜襲う狂おしいまでの欲望はやまない。
ジェラードはミラを四つん這いにさせて尻を打ち、アランは甘く淫らに奉仕し、
連日連夜それぞれが刹那の淫欲にふけり、悶えるミラをなだめるうち、ついにその瞬間が訪れる。ジェラード、アラン、そしてミラが完全に、そして同時に満たされる瞬間が――。 -
2週間前、モリーはアッシュフォード・ホールのメイドに雇われた。
美しい容貌の主アッシュフォード卿は、堕天使さながら気に入らないことがあれば使用人たちを容赦なく怒鳴りつけ、激しく叱責する。
ある日、図書室ではしごのてっぺんに立ち、本の埃取りをしていたモリーは、物音に気づいて振り返った。ご主人様のブルーの目がモリーを見上げていた。
はしごの一番下の段に乗ったご主人様の手が、スカートの下を這い上ってくる。
逃げるべきなのはわかっていた。でも……相手はご主人様だ。
「旦那様、失礼いたしました。あとで戻ってまいります」
「だめだ」ブルーの瞳がきらりと光る。
「まだアッシュフォード・ホールへの歓迎のもてなしがすんでいない」
そう言うとアッシュフォード卿ははしごを上りながら、モリーの真っ白なふくらはぎから太腿へと指を――。 -
★〈12 シェイズ・オブ・ナイト〉から、シリーズおすすめ度No.1のSMエロティカ!★エレノアは“S”の恋人が1週間留守にする間、同じ嗜好を持つ彼の友人ダニエルに貸し出されることになった。ダニエルは“M”の妻を3年前に亡くして以来、雪深いニューイングランドの屋敷に引きこもっているという。愛する恋人から弄ばれるのも、他人の慰みものになるため貸し出されるのも、“M”である彼女の宿命とはいえ、きっと老いぼれた幽霊のような男に違いないと思うと気が重かった。ところが予想に反してダニエルは物憂げな視線がセクシーな30代半ばの男で、エレノアは思わず目を伏せた。7日間だけの“ご主人様”から受けることになる痛みと快感への期待に、既に濡れているのを悟られたくなくて。
-
★エロティカは、ファンタジーを叶える夜だけの魔法。★
私は隣人をのぞき見しながら自慰に耽ることが、もうやめられなくなっていた。2週間前隣に越してきた男は、毎晩帰宅するとカーテンのない窓の前で服を脱ぎ捨て、タトゥーに覆われた筋肉質の体を惜しげもなく披露する。あるときはそのまま股間のふくらみに手を這わせ、またあるときは訪れる美女たちを悶えさせファックするさまを、彼ははばかりもせず見せつけるのだ。裏庭から私が見ているとは思いもせずに。私は彼に気づいてほしかった。彼に犯されたかった。叶わぬ望みに目を閉じ、せつなく募る欲望のままに指を動かす。デッキチェアの上で思いきりイキそうになったとき、力強い手が私の脚を左右に押し広げた。ぎょっとして顔を上げると、目の前に立っていたのは、さっきまで窓の向こうにいたはずの彼――! -
「ボスが、今すぐオフィスへ来いって」
同僚のいつもの言葉に、ウエイトレスのローズの頭はたちまち冷静さを失った。
「わかったわ」か細く上ずった声で答える――そわそわしている様子が表に出ないよう、細心の注意を払って。
分厚いオフィスのドアの奥で革張りの回転椅子にゆったりと腰掛けていたボスが、重々しい口調で静かに言った。
「今日のランチタイムに、冷めた料理をお客に出したそうだね」
全身にぞくりと戦慄が走り、ボスの黒いブーツをじっと見つめる。
「こういうトラブルを起こした者にはお仕置きが必要だとぼくは思うが。どうだね?」
ローズは蚊の鳴くような小さな声で答えた。「はい、ご主人さま……そういうウエイトレスはお仕置きに値すると思います」
「出せ」ボスが命じた。両手を大きな椅子のアームに預け、待ち受けている。
「はい、ご主人さま」ローズはコンクリートの床にひざまずき、ボスの大きく開いた脚の間に体を滑り込ませると、ズボンをゆっくり引き下ろした。
そのとたん、怒張した彼のものが勢いよく飛び出し、獣じみたにおいが一気に立ちこめた。
ボスが喉の奥で低い声を洩らす。「では、きみがどれくらい反省しているか見せてもらおうか。口を開けろ」 -
何もかもうまくいっていた。クライアントのアレックスに、デスクで激しく突き上げられているところをCEOのブルース・デイヴィスに見つかるまでは。40代半ば、情熱的で敏腕で、男として脂ののりきった申し分ないルックスのデイヴィスを、私は上司としてとても尊敬していた。よりによって彼に見られるなんて。だがデイヴィスは、クビを覚悟し彼のデスクの前に立った私を見つめると、絞り出すような声で言ったのだ。「僕も君を欲しいと思っていた」そして、さらに思いがけない告白が続いた。「きみを死ぬほどイカせよう。代わりに、僕を裸にし、気が済むまで足蹴にしてくれないか」と。
-
若く裕福な未亡人ソフィアは、上流婦人の“夜の生活”について助言を受けるため、マダム・シャムフルールの屋敷を訪ねた。
応接間に現れたのは、並はずれて美しい官能的な笑みを浮かべた紳士――アンブローズ・シャムフルール。
彼は相談に訪れる女性を不安がらせないよう女性の名を使っていると明かし、大きな両手で彼女の手を握った。
と、その瞬間、ソフィアの下腹部に淫らな戦慄が走った。
ふしだらにも、彼の指に体のほかの部分をゆっくりとやさしく愛撫される自分の姿が頭に浮かぶ。
ソフィアは頬を真っ赤に染めながら告白した。夫婦の営みに満足を見いだせず、当惑ばかりさせられていた過去を。
「つまり、ご主人は一度も喜びを与えてくれなかったのですね?」
彼はソフィアを立ち上がらせ、つぎつぎに服を脱がせると、シュミーズに包まれた胸のふくらみを指で愛撫しはじめた。
経験したこともない、初めての感覚。
ソフィアは両脚のあいだがゆっくりと脈打ち、濡れていくのを感じて……。 -
囚われの身である私に対して、野獣は常に紳士的に振る舞った。
毎夜プロポーズを拒んでも、彼は決して逆上したりなどしなかった。
だがある晩、うなされる野獣の声にいてもたってもいられず
彼の寝室に飛び込んだ私は、大きな間違いを犯したことを悟る。
野獣は、乳首も脚のあいだの陰りも完全に透けた私のナイトドレス姿を見て
恐ろしいうめき声をあげ、警告した。
「それを破られたくなかったら、むこうを向いて膝をつけ」
恐怖のあまり身がすくんで動けないはずの私の下腹部で
熱い血潮がふつふつと沸きだし、奇妙な疼きが広がる――
私は興奮していた。野獣の猛々しい愛が、欲しくて……。 -
社交界デビュー以来、そそっかしさが仇となり不名誉な評判に悩むグレースは、その日もドレスの裾を踏んで転び、二人連れの紳士をレモネードでびしょ濡れにしてしまった。
二人の紳士は丁重に詫びるが早いか、グレースを近くの部屋に連れていくと……ドアを閉めて施錠した。
グレースは息をのんだ――閉じこめられてしまった! きっと陵辱されるのだ。
「きみに大切な話があるんだ。内密に」えくぼの素敵な紳士はアティクスと名乗り、傍らに立つ美貌の紳士を紹介した。「彼はフィッツジェラルド子爵」
子爵が真っ青な瞳で射抜くようにグレースを見つめ、燃えるような熱い手を太腿にのせてくる。
「ぼくたちは、しばらく前からきみのことを花嫁候補に考えていた」
グレースの心臓がびくんと跳ねた。“ぼくたち”ですって……?
「ぼくたちはすべてを分かち合う――女性も含めてね」
グレースの胸が早鐘を打ち始めた。「あの……つまり……結婚したら、夫婦のベッドにはあなたがたふたりがいる……ということ?」
「そうだ。ふたりできみに触れ、キスをし、舐め、快感で立てなくなるまで突きまくる」 -
1年前に離婚して以来、私の毎日は仕事と家の往復だけという味気ないものだった。
そんな私を憐れんで、親友が誕生日にプレゼントしてくれたのが、
〈恍惚のスパ〉という超高級マッサージパーラーのギフトチケット。
私はさっそく次の週末、凝り固まった体を引きずって〈恍惚のスパ〉を訪れた。
高級感溢れるサロンで迎えてくれたのは、名札に“ハンター”とあるハンサムな男。
裸同然の恰好でうつぶせになり、ハンターにすべてを任せ、マッサージが始まった。
大きな手がお尻を絶妙な力加減で揉みしだく、円を描くように。そして――
えっ、ちょっと待って……こんなマッサージ、合法なの?
思わず体を硬くした私におかまいなしで、彼の指がお尻の割れ目から忍び込んでくる。
始まって10分。その淫らなタッチだけで、ああ、2回もイクことになるなんて……。 -
パトリック・ダヴは、とてもハンサムで有能な私の個人秘書。くせ毛の淡い金髪に、スポーツ選手みたいにしなやかな身体つき。どんなにきつい会議でヘトヘトになっても、彼がデスクの脇で静かに微笑み、「おつかれさまです、ボス」と迎えてくれるだけで、重たい気分は霧のように消え去る。ある日、いつにも増して疲労困憊した私を見かね、パトリックが静かに言った。「あなたを数時間ほど連れ出したほうがよさそうだ」カフェにでも行くのかと顔を上げると、彼は見たこともないまなざしで私を見ている。えっ……もしかして彼、イケナイこと考えてる? 私の脚の間が、じゅっと音をたてたように疼き、彼はそれを見透かしたかのように、かすかな笑みを浮かべた。ええ、そうよ。私をここから連れ去って、車の中でもホテルでもいい、何もかも忘れられるくらいイカせてほしい……!
-
ここはいったいどこ? ヘレンは眠気で朦朧とする頭を起こし、まばたきした。揺れるろうそくの光――
見慣れない部屋だ。身を起こそうとして、愕然とした。縄で腕を縛られている!
「ようやく目が覚めたね」部屋の隅から聞こえてきた低い声の主は……新郎のピアースだ。
ヘレンは父を恨めしく思った――悪名高き放蕩侯爵に娘を嫁がせた父を。
固く立ち上がった乳首をピアースの指がかすめ、ヘレンはあえいだ。「ほら、体はこんなにも正直だ」
レースのナイトガウンの胸元からは乳房があらわになっているし、その下のサテン地も薄く、秘所の茂みまでが透けて見えている。
そのとき、食事の盆を抱え使用人が現れた。ああ、使用人の目に裸同然の新妻の姿をさらすなんて……。
花婿は、ズボンの前のふくらみを大きくした使用人を下がらせてから言った。
「清純ぶるな。その脚を開いて濡れたところにあいつのモノを突っこんでほしそうな顔をしただろう?」
卑猥な言葉に屈辱を覚えながらも、恥ずかしいことにヘレンはその部分が潤ってくるのを感じて……。 -
「ぼくが贈った、あのパンティを履いているんだろう?」
すっかり耳になじんだ声が、低くかすれた響きでささやいてくる。
わたしの体は即座に反応し、脚の間がじゅっと疼く。
こんな電話がかかってくるようになってまだ一週間にもならないけれど、
わたしは彼の言うがまま指先を踊らせ、彼の命令に服従するがまま、
激しくイッてしまうようになっていた。本当はこんな電話、すぐに切りたいのに。
「パンティに縫いつけられているビーズをプッシーにこすりつけろ」
彼の要求は徐々にエスカレートしていく。そしてわたしの興奮も。
スカートをまくりあげ、あられもない姿で激しいオーガズムに達したとき、
突然ドアが開き、入ってきたのは――! -
10年目の同窓会に、会いたい人はただひとり――。
ミスター・ローレンス――高校3年のときの、数学の先生。
当時から、授業中に目が合うたび、ほかの誰とも感じられない何かを感じていた。
先生との間にはきっと何かがある、きっと先生も同じ気持ちでいるはず、と思っていた。
高潔な先生は何もしなかったけれど、私は違う。いつも思い描いていた。
先生が私にキスするところ。先生が私の胸を揉みしだき、いやらしいことを呟く。
もうたまらないというように乱暴に脚を開いて、私の中に入ってくるところ……。
10年経っても色褪せないこの想いを、まさか先生も抱いてくれていたなんて。
当時の教え子に囲まれていた先生は、私を見つけるなり「失礼」と輪を抜けだし、
まっすぐこちらへ歩いてきた。その数十秒後。私たちは廊下の角を曲がるなり、
激しく腰をぶつけ合いながら舌を絡め合っていた――。ひとりの男と女として。 -
ロザリンドは従者も連れず、徒歩でファロン公爵の屋敷にたどり着いた。
“悪魔公爵”と噂される男の屋敷を女が1人で訪れるなど正気の沙汰ではないが、
誰も頼る者のないロザリンドにとって、ファロンだけが残された救いだった。
ギャンブル好きの父は常に金に困っており、金目のものならなんでも売る。
そしていま、娘さえも売り飛ばそうとしているのだ。好色な年寄りの貴族に。
私があの老人のものになるより早くファロンと結婚してしまえば、父も手を出せない。
突拍子もない申し出を携えて現れた娘に、ファロンは思いがけない提案をした。
妻としてふさわしいかを見る試験に合格すれば、おまえを娶ってもいいと。
いったいどんな“試験”なのかとロザリンドがおそるおそる訊くと、公爵は答えた。
「おまえがわたしの愛撫によって絶頂に達するところを見たい」
一般館に書籍が 124 件あります。
・キャンペーンの内容や期間は予告なく変更する場合があります。
・コインUP表示がある場合、ご購入時に付与されるキャンペーン分のコインは期間限定コインです。詳しくはこちら
・決済時に商品の合計税抜金額に対して課税するため、作品詳細ページの表示価格と差が生じる場合がございます。